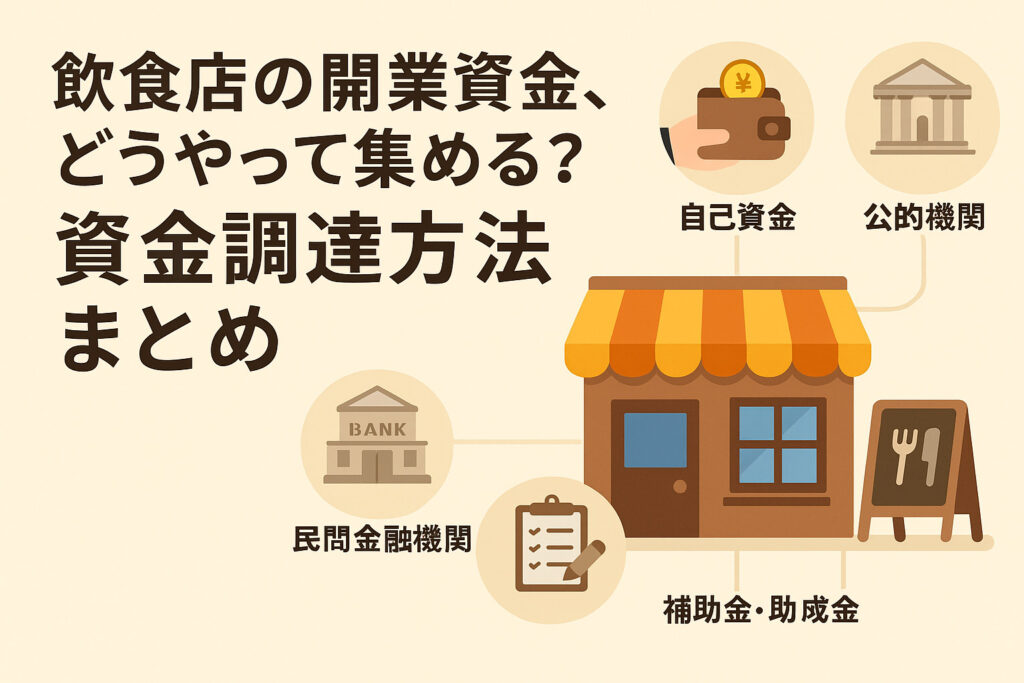
飲食店を立ち上げるには、決して少なくない資金が必要です。物件取得費や内装工事、設備投資、そして開業後の運転資金…。これらをすべて自己資金だけでまかなうのは現実的ではない場合も多いでしょう。
そこで今回は、飲食店の開業時に活用できる資金調達の選択肢と、それぞれの特徴や注意点について解説します。これからお店を持ちたいと考えている方、資金面で不安を抱えている方にとって、事前に知っておくべき大切な情報です。
自己資金だけでは危うい? 開業資金の落とし穴
飲食業界では「開業後2年以内に約6割が閉店」という厳しいデータもあります。その原因の多くが、初期投資のしすぎや、運転資金の不足。つまり、「開業はできても、継続が難しい」ということです。
そのため、資金調達は“開業準備”の一環ではなく、“経営の土台作り”と捉えて計画的に行うことが重要です。
飲食店開業に必要な費用の目安
飲食店を始めるには、平均して1,000万円前後の資金が必要と言われています。
昨今の建築費の高騰を考慮すると居抜き物件出ない場合は、1,000万円を超える資金が必要になるでしょう。
・物件取得費(保証金や礼金、仲介手数料など)
・内装・厨房設備などの工事費
・開業後数ヶ月分の運転資金(家賃・仕入・人件費・広告費など)
これらすべてを自己資金だけで賄えるケースはまれです。だからこそ、「融資」や「補助金」など、外部からの資金調達を組み合わせて考える必要があります。
そのため、資金調達は“開業準備”の一環ではなく、“経営の土台作り”と捉えて計画的に行うことが重要です。
飲食店開業に必要な費用の目安
飲食店を始めるには、平均して1,000万円前後の資金が必要と言われています。
昨今の建築費の高騰を考慮すると居抜き物件出ない場合は、1,000万円を超える資金が必要になるでしょう。
・物件取得費(保証金や礼金、仲介手数料など)
・内装・厨房設備などの工事費
・開業後数ヶ月分の運転資金(家賃・仕入・人件費・広告費など)
これらすべてを自己資金だけで賄えるケースはまれです。だからこそ、「融資」や「補助金」など、外部からの資金調達を組み合わせて考える必要があります。
主な資金調達の方法と特徴
自己資金:融資=3:7(=自己資金30%以上)が、最も現実的かつ金融機関にも信頼されやすいバランスです。したがって、開業費用の1/3くらいは自己資金として用意をしておきましょう。
自己資金はいくら必要?(開業費用1,000万円の場合)
開業費用総額 自己資金(30%) 融資(70%)
1,000万円 約300万円 約700万円
800万円 約240万円 約560万円
600万円 約180万円 約420万円
👉 飲食店の開業費用は業態や規模によって異なりますが、自己資金200~300万円を目標に貯めておくと、融資申請時の審査通過率も上がります。
自己資金はいくら必要?(開業費用1,000万円の場合)
開業費用総額 自己資金(30%) 融資(70%)
1,000万円 約300万円 約700万円
800万円 約240万円 約560万円
600万円 約180万円 約420万円
👉 飲食店の開業費用は業態や規模によって異なりますが、自己資金200~300万円を目標に貯めておくと、融資申請時の審査通過率も上がります。
1. 日本政策金融公庫など公的機関からの融資
開業を目指す方の強い味方が、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。
・無担保・無保証で借りられる可能性あり
・創業前から申請可能
・金利が民間よりも低め
特に「若者・女性・シニア」向けの優遇制度も用意されています。
注意点:審査はあります。希望額すべてが通るとは限らず、事業計画書や自己資金の内容によって大きく左右されます。
・無担保・無保証で借りられる可能性あり
・創業前から申請可能
・金利が民間よりも低め
特に「若者・女性・シニア」向けの優遇制度も用意されています。
注意点:審査はあります。希望額すべてが通るとは限らず、事業計画書や自己資金の内容によって大きく左右されます。
2. 自治体の補助金・助成金
補助金:審査あり。採択されれば高額な支援を受けられる
助成金:条件を満たせば原則支給(先着順が多い)
どちらも返済不要という点が魅力です。ただし、支給タイミングが遅く、開業前には使えないことが多い点には注意が必要です。
たとえば、以下のような制度があります:
・東京都の「創業助成事業」
・中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」
・「IT導入補助金」など
制度は随時更新・終了することもあるため、最新情報をチェックしておきましょう
助成金:条件を満たせば原則支給(先着順が多い)
どちらも返済不要という点が魅力です。ただし、支給タイミングが遅く、開業前には使えないことが多い点には注意が必要です。
たとえば、以下のような制度があります:
・東京都の「創業助成事業」
・中小企業庁の「小規模事業者持続化補助金」
・「IT導入補助金」など
制度は随時更新・終了することもあるため、最新情報をチェックしておきましょう
3. 民間金融機関からの融資
■ プロパー融資(直接融資)
銀行が独自の基準で審査・融資します。実績がない開業時は通りにくいため、慎重な対応が必要です。
■ 制度融資(自治体 × 信用保証協会)
自治体・銀行・保証協会が連携する制度で、開業時でも借りやすく、低金利・無担保・連帯保証人不要というメリットもあります。
注意点としては、3機関が関わるため、審査期間が2〜3ヶ月と長くなる点です。
■ 信用保証付き融資
保証協会の保証がつくため、融資のハードルがやや下がりますが、保証料が自己負担となります。
銀行が独自の基準で審査・融資します。実績がない開業時は通りにくいため、慎重な対応が必要です。
■ 制度融資(自治体 × 信用保証協会)
自治体・銀行・保証協会が連携する制度で、開業時でも借りやすく、低金利・無担保・連帯保証人不要というメリットもあります。
注意点としては、3機関が関わるため、審査期間が2〜3ヶ月と長くなる点です。
■ 信用保証付き融資
保証協会の保証がつくため、融資のハードルがやや下がりますが、保証料が自己負担となります。
4. 親族や知人からの支援
知人や家族からの資金提供は、金利や審査が不要な分、スムーズな調達が可能です。
返済義務がない贈与:贈与契約書を作成し、税務上のトラブルを避けましょう
返済が必要な場合:借用書の作成を。曖昧なやりとりは後々の関係悪化につながります
返済義務がない贈与:贈与契約書を作成し、税務上のトラブルを避けましょう
返済が必要な場合:借用書の作成を。曖昧なやりとりは後々の関係悪化につながります
5. クラウドファンディングの活用
インターネットで支援者を募る方法です。
資金調達と同時に、お店の宣伝や事前ファンづくりにもつながります
成功にはストーリーや魅力的なリターン設計がカギ
ただし、目標金額に届かないケースや、支援金の使途の透明性などにも気を配る必要があります。
資金調達と同時に、お店の宣伝や事前ファンづくりにもつながります
成功にはストーリーや魅力的なリターン設計がカギ
ただし、目標金額に届かないケースや、支援金の使途の透明性などにも気を配る必要があります。
開業資金の準備は「今すぐ」始めよう
飲食店開業を目指すなら、資金調達は早めに動くのが鉄則。開業してからでは融資の審査基準が厳しくなり、資金ショートのリスクも高まります。
また、自己資金は融資審査のうえでも重要な判断材料になります。コツコツと蓄えた記帳済みの預金が、あなたの“信用”を支える武器になるのです。
また、自己資金は融資審査のうえでも重要な判断材料になります。コツコツと蓄えた記帳済みの預金が、あなたの“信用”を支える武器になるのです。
まとめ:資金調達もまた「経営」の第一歩
飲食店のスタートに必要なのは、「美味しい料理」だけではありません。健全な資金計画こそ、成功のレールを敷く第一歩です。
不安や疑問がある方は、ぜひ専門家のサポートを受けてください。開業支援のプロとして、資金調達から補助金活用、融資の申請書作成まで、あなたのスタートを全力でサポートいたします。
不安や疑問がある方は、ぜひ専門家のサポートを受けてください。開業支援のプロとして、資金調達から補助金活用、融資の申請書作成まで、あなたのスタートを全力でサポートいたします。

